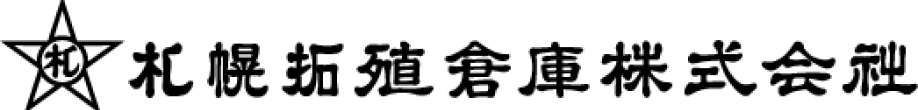駅裏8号倉庫の起こり
相談役 池田顕 インタビュー
1年で壊してしまう倉庫なら、
有効に使ってもらおう
昭和58年(1983年)31歳で社長に就任しました。私自身を振り返ると、学生時代には芝居の脚本を書いたり映画を撮ったりしていました。その頃から創作活動には関心がありました。大学卒業後は札幌で喫茶店を開いていたのですが、それも企業に入って仕事をするより、自分で店をやってみたいと思ったことが理由です。しかし父だった当時の社長が体調を崩したため喫茶店を閉じ、入社前の修行として東京の倉庫会社で1年の勤務したのち札幌拓殖倉庫に就職しました。
石造倉庫群をとりまく環境
旧本社倉庫は北6条西1丁目に5棟並ぶ明治時代に造られた石造倉庫群でした。当時の社会情勢として、鉄道輸送から自動車輸送への転換期でもあったため、大型トラックの搬入が容易になるような改築を検討していました。しかし、旧国鉄函館本線の高架化計画用地のため「収用対象の建物の改造は控えるように」との申し入れがあったのです。降雪量の多い札幌の地において、積雪期間は搬入作業に苦労し、利用が困難な状況でした。アクセスの良い場所にはあったのですが、老朽化した建物のため賃貸料は満足する水準になく活用方法に苦慮していました。
昭和47年(1972年)札幌市から石造倉庫群は収用されるので協力するよう正式に要請がありました。しかしその後の経済情勢悪化などにより計画は遅々として進まず、厳しい経営状況が続きました。その後、昭和55年(1980年)から札幌市高架部との収用交渉が始まり、翌56年から57年にかけて石造倉庫群は解体収用されることになりました。

ある劇団との出会い
そのような状況下で、劇団53荘を主催する植田研一氏より「稽古場を探しており、石造倉庫を貸して欲しい」との提案がありました。しかしこの建物は営業倉庫(倉庫を営業目的で使用すること)として国に申請を出しており、不動産賃貸の用途で使用することはできなかったのです。一度はお断りしたのですが、取り壊しまであと1年半となった時に営業倉庫としての許可を返納したことで、稽古場としての貸し出しが実現しました。昭和56年(1981年)8月から翌年11月までの期間限定で、駅裏8号倉庫がオープンしたのです。

なぜアーティストが集まったのか
当時の賃料は月に15万円で、年間180万円が必要でした。1つの劇団が借りるには決して少ない額ではありません。そのため、劇団53荘を中心に、シアターキノ代表の中島洋氏を始め、ミュージカルや音楽・映像関係の各所に声をかけ、運営委員会方式で借りることとなりました。結果として多くのアーティストが集まり、札幌の文化芸術の発信地となったのです。当時専務(前社長)だった私も、自らの学生時代には映画制作や脚本の執筆などに熱を入れたこともあり、サブカルチャーには理解がありました。いろいろな要因が絡み合い生まれた劇場空間は、その立地から「駅裏8号倉庫」と呼ばれました。今でもそこで生まれた数々の逸話が語り継がれています。

倉庫という異空間が、
自由で創造的な感動を生んだ
当時の演劇といえばテントで行うことはありましたが、倉庫を舞台にした空間は稀でした。明治時代に建てられた市内最古の石造り倉庫、そういった異空間が新鮮な感動を生み、アーティストに評価されたのだと思います。観客の方にとっても、劇場とは異なる空間に集うワクワク感があったのではないでしょうか。また機能面でも石造りの建物は防音に優れており、自由に大きな音を出せる場として適していました。解体期限とともに役目を終えた駅裏8号倉庫は、昭和58年(1983年)に北海道開拓の村に寄贈され、保存展示されることとなりました。